横断型人文学プログラム
- Home
- 横断型人文学プログラム
- プロジェクト・ゼミ
プロジェクト・ゼミ
身体・スポーツ文化論コース

保健体育研究室(2022年度以降、基盤教育センター身体知領域)の島健先生によるプロジェクト・ゼミです。
ゼミ全体のテーマは、「現代社会における共生社会をめぐる問題―身体やスポーツの観点から―」。
今回は、順天堂大学の野口亜弥先生をゲストにお迎えし(Zoomでのご参加)、スポーツにおけるジェンダー・セクシュアリティの問題について理解を深めていきました。
競技スポーツの世界には、筋肉を強くするテストステロン値が高ければ男性、低ければ女性とみなす考え方が存在し、性別にかんする疑いの眼は、女性アスリートとして活躍する選手(出生時は男性)ばかりか、生まれながらにテストステロン値が高い女性アスリート(高アンドロゲン症の女性)にまで向けられます。
男性よりも女性の方が身体的に劣っているという前提のもとに設けられた判断基準であることは明白であり、公平性を担保するためにアスリートが積極的に問題提起をする必要性について、活発な意見交換がなされました。
芸術文化論コース
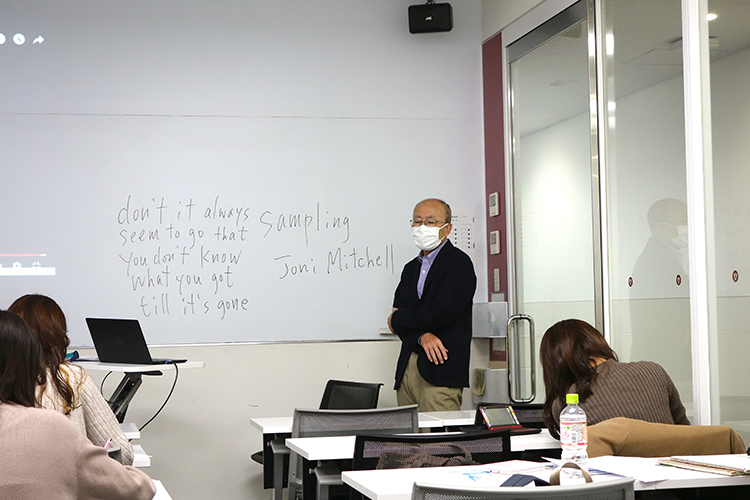
英文学科の飯野友幸先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「Black Lives Matter (BLM) 研究―黒人音楽を中心に―」。
Black Lives Matter(ブラック・ライブズ・マター)とは、アフリカ系アメリカ人に対する警察の残虐行為をきっかけにアメリカではじまった人種差別抗議運動を指します。
取材でお邪魔した日は、主に、サンプリング(まったく違う曲を混ぜて、政治・社会的メッセージ性のあるものに仕上げる制作手法)についてのお話を伺いました。先生がおっしゃるには、モダニズム文学に古典の要素を入れるのと似たような手法であるとのこと。
実際に、ロックバンドエアロスミスの「ウォーク・ディス・ウェイ」(Walk This Way, 1975)を、ヒップホップ・グループのラン・ディーエムシーが1986年にラップでカバーした曲や、ジョニ・ミッチェルの「ビッグ・イエロー・タクシー」(Big Yellow Taxi, 1970)をサンプリングしたジャネット・ジャクソン「ゴット・ティル・イッツ・ゴーン」(Got 'til It's Gone, 1997)のミュージックビデオを観る時間もありました。
ジャパノロジー・コース

史学科の北條勝貴先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「フィールドワークで探る列島文化の多様性」。
今回は、浅草から吉原までの道を、かつて吉原遊郭へと向かう客が利用した水上路(山谷堀)に沿って辿りながら、道の途中にある史跡を巡りました。
残存する吉原遊郭の石垣の一部(写真参照)や、遊女たちが信仰した吉原弁財天、浄閑寺にある遊女慰霊碑(新吉原総霊塔)など、悲しい歴史に思いを馳せさせる様々な出会いがありました。
芸術文化論コース

ドイツ文学科の三輪玲子先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「舞台芸術の意義と可能性―創造から鑑賞まで―」。
受講生たちは、ひと通りの知識を学んだ後、自分の関心に基づいて各自テーマを設定し(学校教育の中の演劇、能演劇における身体表象等)、発表を行います。
ジャパノロジー・コース

哲学科の寺田俊郎先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「日本文化論を編みなおす」。
河合隼雄『日本文化のゆくえ』(2000)の中のひとつの章「学校のゆくえ」をもとに、学校教育の在り方について活発な議論が交わされました。
評価できることしか教えない(例えば、「哲学対話」は評価しにくいため、高校のカリキュラムに導入されない)、形式的な質疑応答に終始するシステム化された授業が、目的意識を持たずにレベルだけで大学を選ぶ現象を引き起こしているというお話には、受講生全員が共感したのではないでしょうか。
身体・スポーツ文化論コース

保健体育研究室(2022年度以降、基盤教育センター身体知領域)の吉田美和子先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「身体文化としてのスポーツ、ダンス、 そして日常を生きる『からだ(Soma)』を考える」。
今回は、舞踊家の岩下徹先生をゲストにお迎えしての授業でした。
岩下先生によれば、踊りとは、考えながらするものでも、強制されてするものでもありません。「何々を表現する」の「何々」(目的)を排除し、内から押し出されたものをそのまま「表出する」のが踊りです。
踊りはまた、「自身が癒える力」(癒されるのでなく、自分で治す力)にもなります。フランスのブロワにあるラ・ボルド精神病院で、岩下先生が医師、スタッフ、患者さんたちを前に踊られている動画には、攻撃的な動きをしていたある患者さんの身体が、先生と共振するように、踊りの身体へと少しずつ変化していく様子が映っていました。
吉田先生がいつもおっしゃっている、物としての身体(Body)ではない、身体・心・スピリチュアリティを含むからだ(Soma)の存在を感じることができた時間でした。
芸術文化論コース(舞台芸術)

英文学科の西能史先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「映画で学ぶシェイクスピアの英国歴史劇」。
アメリカの映画監督兼俳優であった鬼才オーソン・ウェルズ (1915-85) が手掛けた映画『真夜中の鐘』(1965) について考察していきました。
『真夜中の鐘』は、シェイクスピア『ヘンリー四世』を脚色した作品で、ウェルズ自身が、主人公のフォルスタッフを演じています。
『ヘンリー四世』を知っているという前提でストーリーが展開する、パッと見ただけでは面白さがわからない等の理由から、興行的には不成功に終わりました。しかし、インタビューのなかで、ウェルズは、映画というものは、見返すたびに新しい発見があるほどのディテールにあふれていなければならない、と熱く語っています。
講義ではさらに、ウェルズが主宰していたマーキュリー劇団を舞台にした映画『僕と彼女とオーソン・ウェルズ』(2008)の一部を観賞しました。
映画のなかには、マーキュリー劇団が実際に公演を行ったシェイクスピア『ジュリアス・シーザー』の稽古の模様が描かれているのですが、注目すべきは、役者がファシストの制服で登場するという演出です。
1930年代当時の状況と重ね合わされることでより緊張感が高まったシーザーの世界を、当時の観客たちはどのように受け止めていたのでしょうか。
芸術文化論コース(音楽芸術)

ドイツ文学科の佐藤朋之先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「『ロマンティック』を考える―― ロマン主義アートの観かた、聴きかた、読みかた――」。
今回は、ゲストスピーカーとして、著述家の明石政紀先生をお招きし、ロマン派の音楽についてお話しいただきました。
均整や調和といった形式を重んじる古典派とは対照的に、ロマン派の音楽は、感情のゆらぎやうねりといった、人間の内面を表現します。
ベートーヴェンにはじまり、90年後のマーラーで終焉を迎えたロマン派でしたが、感動を求める聴衆は、その後も、ロマン派の音楽を好みつづけました。実際、映画音楽の大半やポップミュージックにも、ロマンティシズムは息づいています。
講義のなかでは、ダグラス・サーク監督の映画『天はすべて許し給う』(1955)が紹介されました。当時としてはありえない年上の女性(未亡人)と若い庭師の恋を描いたメロドラマで、しかもわざとらしいハッピーエンドで締めくくられるにもかかわらず、映画内で使用されたブラームスとリストの曲の効果も相まって、公開当初は感動の嵐を呼びました。
ところが、つづく明石先生のお話によれば、ダグラス・サーク監督は元々、反ロマン主義の人であるとのこと。
人間の感情を操作できるというロマン派の音楽の危険性を、敢えて操作してしまう(感動させてしまう)ことで伝えようとする大胆な手法には、驚かされるばかりです。
ジャパノロジー・コース ①

ドイツ文学科のドゥッペル・メヒティルド先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「越境文学――日本文学の多様性を考える」。
多民族のヨーロッパには、母語とは異なる言語で書かれた文学が多く存在しますが、日本にも、日本語を母語としない作家が日本語で書いた文学(日本語文学)が存在します。
今回扱ったテクストは、リービ英雄『模範郷』。主人公の「ぼく」が、半世紀ぶりに、台湾にある故郷「模範郷」へ帰るという内容ですが、「ぼく」は明らかに作家自身であるうえ、実在の人物も登場することから、果たして小説なのか、旅行記なのか、と考えさせられる作品です。
日本語を母語としない作家によって書かれたとは思えないほどよどみのない、美しい文章でしたが、「やかん」が、ルビを振って「薬缶」と表記されているところなどには、作家のアイデンティティがよくあらわれているという先生のご説明がありました。
ジャパノロジー・コース ②

新聞学科の碓井広義先生によるプロジェクト・ゼミです。
テーマは、「脚本家・倉本聰と日本のテレビドラマ」。
シナリオという観点から、日本のテレビドラマについての考察を深めていく授業ですが、ただシナリオを読むだけではありません。ゼミの期間中に、受講生たちは、各自、オリジナルのシナリオを2本実作します。
取材にお邪魔した回は、1作目のシナリオの発表会でした。先生から出されたお題は「鼻」。芥川龍之介『鼻』を脚色するという試みです。
舞台設定が、原作の寺から、学校や長崎の教会になったり、主人公の設定が、鼻にコンプレックスを持った男から鬼になったりと、完成したシナリオは、いずれも、各自の個性が光る面白いものでした。

